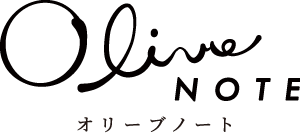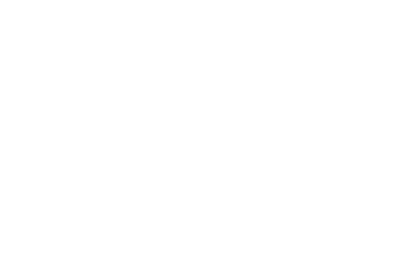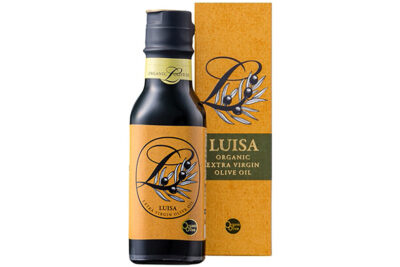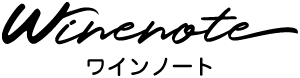手作りクラフトコーラでおうちカフェを満喫!
目次

最近よく聞くクラフトコーラ。専門店をちらほら見かけたり、成城石井などのお店でもコーラシロップを見かけるようになりました。そこではじめて「コーラって何でできているんだ?」という疑問を持つようになりました。
調べてみるとスーパーで買える食材で手作りコーラが作れるようなので、チャレンジしてみました。作ってみるといいことばかり。今年の夏は手作りのクラフトコーラでおうちカフェを楽しみたいと思います。
手作りクラフトコーラのレシピ
材料(作りやすい分量:約8杯分)
- 砂糖 200g
- 水 200g
- ホールクローブ 20粒
- カルダモンシード 10粒
- シナモンスティック 1本
- レモン 1個
- バニラエッセンス 5滴

作り方
1. レモンはよく洗い、輪切りにする。できればノーワックスのものを購入しましょう。
2. シナモンスティックを半分に折る。カルダモンシードもキッチンばさみで刻み、クローブと一緒に鍋に入れる。

3. 2に砂糖、水、レモンを加え弱火で加熱する。

4. 10分ほど加熱したら火を止め、バニラエッセンスを加える。

5. あら熱が取れたら、清潔な容器に入れて冷蔵庫で保存。2週間を目安に飲みきるようにしましょう。

本当にコーラが作れるのか?と半信半疑で作りましたが、スパイスを用意している時から何となくコーラの香りが。鍋を火にかけると、よく知っているコーラの香りが部屋中に漂ってきました。

作りたてすぐもいいですが、冷蔵庫で1日ほど置くと味がなじんで飲み頃になります。またシロップを作った際、レモンやスパイスなどはそのまま一緒に漬け込むことで、よりおいしくなります。わたしは飲む際、茶こしで濾して飲んでいます。
市販のコーラと飲み比べてみました

香りはコーラそのものですが、色がかなり薄く、本当にコーラの味はするの・・・?と心配に。そこで市販のコーラと飲み比べてみました。手作りのクラフトコーラシロップは、無糖の炭酸水で3倍に割りました。
飲んでみると市販のものよりさっぱりしていて、レモンやスパイスの味を感じます。甘みは同じくらいに感じました。市販のものはカラメル色素が入っていてコーラの濃い色をつけているので、見た目は違いますが味は個人的に手作りシロップの方が好みです。
今回は三温糖で作ったのでうっすら色が付いていますが、グラニュー糖で作るとさらに薄い色に、反対に黒糖で作ると市販のコーラに近い色味になります。砂糖の種類を変えて好みの味を見つけるのも楽しみになりますね。
手作りクラフトコーラのメリット
材料を揃える必要はありますが、作る手間はなく簡単に作れます。手作りクラフトコーラには、ほかにもこんなメリットがあります。
好みの甘さ・味にできる
シロップを割って飲むので、好みの濃さにできるのがポイント。甘すぎるのは苦手、スパイシーにしたいなど、自分の好みで作ることができます。
好きなもので割って飲める
無糖の炭酸水のほかに、グレープフルーツなど柑橘系の風味がついた炭酸水で割るとさらに爽やかな味わいに。ほかにもこんな活用方法があります。
- 原液を割らずにかき氷にかければ、コーラ味のかき氷に
- 冬は体ポカポカホットコーラで
- ハイボールと合わせてコークハイボールに
- ラムと合わせてラムコークに
ヨーグルトにかけたり、牛乳と割るのも人気のよう。無調整豆乳で割れば、コーラ味の豆乳飲料もできます。
炭酸が抜けずにいつでもできたて!
コーラは好きだけどいつも飲みきれず炭酸が抜けてしまう、なんて悩みはありませんか。都度割って飲むクラフトコーラはいつでもできたて。炭酸が抜けずに楽しめますよ。
今回使用したスパイス

今回使用したスパイスはシナモン、クローブ、カルダモンです。シナモン以外は聞き慣れない、カレーに入っているなどざっくりとしたイメージしかない方も多いのではないでしょうか。ひとつひとつ解説していきます。
●シナモン
アップルパイやクッキーなど、スイーツによく使用されるスパイスです。甘く独特な香りが特徴で、チャイティーなどにも使われます。
●クローブ
お菓子や肉料理など幅広く使えるスパイスです。香りは甘みが強く、スパイシーな風味が特徴です。
●カルダモン
カレーに使われることの多い、爽やかな香りが特徴のスパイスです。甘い風味でケーキやクッキーにも活用されます。
今回は全てホール(粒)のものを使用しました。パウダー状のものも販売されていますが、粒の方がよりスパイスの風味を感じることができます。また刻んだり折ったりすることで、より香りが強くなります。
好みのスパイスや柑橘でアレンジ
今回は比較的手に入りやすいスパイスで作りましたが、ほかにもさまざまなスパイスや柑橘を使って作ると違った味わいになります。
レモンをライムに変えることでよりエキゾチックな味わいに、すだち、ゆずに変えることで和風の味わいに。甘さを求めるならオレンジやグレープフルーツもおすすめです。生姜の薄切りや山椒の実を加えるのもいいですね。
バニラエッセンスはバニラビーンズにすることでより甘く濃厚な香りを味わえます。スパイスも広く色々なものが使われ、黒胡椒や八角、ナツメグ、アニスシードなどで作るレシピもあります。
また貴重ですがコーラナッツというものもあります。コーラという植物の実で、この実を原料に作られたものがコーラと言われています。現在コーラナッツが原料のコーラはほとんど製造されていませんが、クラフトコーラの中にはこのコーラナッツにこだわって作っているものもあるので、ぜひチェックしてみて下さいね。
記事:矢崎 海里
人気の記事(ランキング)
 小さな新じゃがいもで作るおかずとおつまみ
小さな新じゃがいもで作るおかずとおつまみ 【2025年版】プロテインの持ち運びに神!ダイソーの粉ミルクストッカーが100均最強だった理由5選
【2025年版】プロテインの持ち運びに神!ダイソーの粉ミルクストッカーが100均最強だった理由5選 また食べたい!ボリュームたっぷりの大人気繁盛店の冷たい肉そばを再現
また食べたい!ボリュームたっぷりの大人気繁盛店の冷たい肉そばを再現 スタバのラップサンドを再現!自家製「トルティーヤ」レシピ
スタバのラップサンドを再現!自家製「トルティーヤ」レシピ 旬の大盛りパセリを大量消費するレシピ3選
旬の大盛りパセリを大量消費するレシピ3選 【プロが教えるおうちパスタ】生クリームは使わない!濃厚なレモンクリームのパスタ
【プロが教えるおうちパスタ】生クリームは使わない!濃厚なレモンクリームのパスタ 虫喰い大葉も大量消費できる!大葉にんにく辛味噌
虫喰い大葉も大量消費できる!大葉にんにく辛味噌 もちもちチャバタはイタリアの高加水パン、簡単レシピで焼き目もシマシマ
もちもちチャバタはイタリアの高加水パン、簡単レシピで焼き目もシマシマ シェフが教える冷静パスタを美味しくするコツ!生ハムとモッツァレラのトマトソース冷製パスタ
シェフが教える冷静パスタを美味しくするコツ!生ハムとモッツァレラのトマトソース冷製パスタ 冷静パスタのポイント付き!タコとトマトの冷製ジェノベーゼパスタ
冷静パスタのポイント付き!タコとトマトの冷製ジェノベーゼパスタ
オイル
料理のジャンル
- お弁当
- 調味料
- うどん
- 韓国料理
- ファイトケミカル
- おせち料理
- マリネ
- 中華
- そうめん
- 漬物
- ステーキ
- グラタン
- エスニック
- 洋食
- おにぎり
- アヒージョ
- 丼
- 食べるオリーブオイル
- カルパッチョ
- そば
- 唐揚げ
- トースト
- お菓子
- マフィン
- 麺
- オーブン料理
- 温野菜
- ローフード
- ハンバーガー
- アイスクリーム
- 椀物
- 土鍋
- ハンバーグ
- BBQ
- 食べるラー油
- 煮物
- 燻製
- ローストポーク
- おやつ
- パウンドケーキ
- アジアン
- ドイツ料理
- 混ぜご飯
- 天ぷら
- デザート
- リゾット
- ちらし寿司
- ディップ
- 調味油
- 煮込み
- 焼肉
- グリル
- ガレット
- パンケーキ
- ダッチベイビー
- ハワイアン
- 雑炊
- ムニエル
- マヨネーズ
- マグロ
- 海苔巻き
- キッシュ
- シチュー
- すし
- ポワレ
- クッキー
- 炒め物
- ホイル焼き
- いなり寿司
- だし巻き卵
- スムージー
- 春巻き
- グリル野菜
食材
- トマト
- チーズ
- 玉ねぎ
- にんにく
- 卵
- 鶏肉
- ベーコン
- 豚肉
- ニンジン
- じゃがいも
- キャベツ
- きゅうり
- 牛乳
- お米
- ナス
- 豆腐
- エビ
- 大根
- チョコレート
- いちご
- さつまいも
- アボガド
- レモン
- ブロッコリー
- 白菜
- ウインナー
- 生ハム
- きのこ
- あさり
- ねぎ
- 大葉
- ズッキーニ
- アスパラガス
- サーモン
- しらす
- 鮭
- かぼちゃ
- パプリカ
- バジル
- 鶏むね肉
- 牛肉
- レンコン
- 菜の花
- 長ねぎ
- ごぼう
- 柿
- レタス
- タケノコ
- ツナ
- ひき肉
- しめじ
- ソーセージ
- くるみ
- バゲット
- 塩麹
- ピーマン
- カツオ
- はちみつ
- 生姜
- 生クリーム
- 強力粉
- みょうが
- ヨーグルト
- クリームチーズ
- ほうれん草
- 薄力粉
- 鷹の爪
- かぶ
- ホタテ
- パセリ
- 納豆
- マグロ
- オクラ
- ハム
- 梅
- 抹茶
- タコ
- もやし
- 梅干し
- 鯛
- わかめ
- バター
- 枝豆
- 小麦粉
- 牡蠣
- 海苔
- アーモンド
- そうめん
- リンゴ
- 水菜
- マヨネーズ
- 缶詰
- サバ
- コーヒー
- セロリ
- しそ
- サバ缶
- 豚ひき肉
- 豆乳
- 小松菜
- キウイ
- さんま
- オリーブ
- 餅
- パン
- そら豆
- ブリ
- バナナ
- 豚バラ
- とうもろこし
- ミニトマト
- 米粉
- ナッツ
- みかん
- ドライイースト
- アジ
- 味噌
- ごま
- たらこ
- キムチ
- 山椒
- イカ
- マッシュルーム
- ちくわ
- カリフラワー
- エリンギ
- 栗
- アンチョビ
- 里芋
- レバー
- 油揚げ
- レーズン
- マスタード
- 柚子
- メイプルシロップ
- ホタルイカ
- スナップエンドウ
- ツナ缶
- ホットケーキミックス
- ニラ
- 鶏もも肉
- しいたけ
- オートミール
- あんこ
- 豆苗
- えのき
- ささみ
- スイカ
- 食パン
- タラ
- セリ
- ブルーベリー
- オレンジ
- きな粉
- ベビーリーフ
- ひじき
- 片栗粉
- まいたけ
- コーン
- 新玉ねぎ
- コンビーフ
- いわし
- グレープフルーツ
- 酒粕
- パン粉
- 昆布
- コチュジャン
- 舞茸
- ちんげん菜
- トマト缶
- 合い挽き肉
- 明太子
- 日本そば
- 桃
- いちじく
- ちりめんじゃこ
- 長芋
- シナモン
- ローズマリー
- 甘酒
- 砂糖
- ナンプラー
- カレー粉
- カシューナッツ
- かに
- ブロッコリースプラウト
- プリン
- ミックスベジタブル
- ゴーヤ
- キヌア
- とろろ
- マスカット
- ししゃも
- イクラ
- クレソン
- 桜えび
- マンゴー
- 大豆
- おから
- かまぼこ
- マーマレード
- イサキ
- 唐辛子
- 寒天
- ふき
- 春キャベツ
- ししとう
- 青のり
- 春雨
- ドライフルーツ
- ライスペーパー
- 餃子
- みつば
- パイシート
- パクチー
- 青しそ
- ぶどう
- こんにゃく
- 黒豆
- 鶏ひき肉
- アーモンドプードル
- ビーツ
- サヤエンドウ
- 山椒の実
- 手羽元
- なめこ
- インスタントコーヒー
- 紫玉ねぎ
- タコス
- ミックスベリー
- ハラペーニョ
- 焼き鳥
- フムス
- テンペ
- 唐揚げ
- ドライトマト
- カップ麺
- アイスプラント
- ピーナッツ
- 福豆
- グリンピース
- しらたき
- 豚しゃぶ
- からすみ
- ラズベリー
- ラフランス
- ケール
- 百合根
- ハマグリ
- ミックスナッツ
- キャラメル
- コチジャン
- ノビル
- 山菜
- わさび菜
- 松の実
- 貝
- チャーシュー
- メロン
- パイン
- 黒蜜
- 豆
- 紫キャベツ
- すり身
- ヤリイカ
- リーフレタス
- 醤油麹
- 新じゃが
- ラーメン
- 親鶏
- 牛もも肉
- 鰹節
- 豚ミンチ
- モッツァレラチーズ
- カマンベールチーズ
- 秋ナス
- イカスミ
- 干し柿
- 白ねぎ
- 青ねぎ
- ヨモギ
- 春菊
- さわら
- ひよこ豆
- ほっけ
- セイヨウカラシナ
- めんつゆ
- ふきのとう
- お茶
- シーフードミックス
- インスタント麺
- 温泉たまご
- ほうじ茶
- さやいんげん
- パイナップル
- はんぺん
- オイスターソース
- 焼きそば
- 紅茶
- すだち
- オレガノ
- うなぎ
- モロヘイヤ
- 新米
- しじみ
- あさり缶
- マスカルポーネチーズ
- 春巻きの皮
- ココア
- 野沢菜
- 鴨
- 山芋
- 魚肉ソーセージ
- 小豆
- ヌテラ
- マシュマロ
- ビスケット
- タラの芽
- きくらげ
- コンビニおにぎり
- フライドチキン
- ポテトチップス
- ウニ
- 鶏レバー
- 酢
- お麩
- 刺身
- 真鯛
- 木の芽
- アイス
- いんげん豆
- 中力粉
- コッペパン
- 砂肝
- 大根葉
- 準強力粉
- 全粒粉
- 穴子
- ベーキングパウダー
- もち麦
- 紫芋パウダー
- いわし水煮缶
- スパゲッティ
- イングリッシュマフィン
- オレンジジュース
- 炭酸水
- ゼラチンパウダー
- アガー
- アイスクリーム
- バターナッツかぼちゃ
- らっきょう
- ミント
- サラダ豆
- 梨
- マカロニ
- カンパチ
- 粉チーズ
- 鶏軟骨
ライフスタイル
- 料理のテクニック
- デリスタグラマー
- 食レポ
- キッチン
- 100均
- ダイエット
- 家のみ
- カルディ
- コンビニ
- オイルの知識
- ダイニング
- オリーブオイル専門店
- パーティ
- リビング
- クリスマス
- ちょい足し
- お正月
- スタバ
- 時短
Olivenoteへようこそ
ヘルシーで様々な効能を持ったオイルへの注目が高まっています。中でもオリーブオイルの消費量は大きく伸び、同時に、ココナッツオイル、アルガンオイル、亜麻仁油、MCTオイルなど、なじみのなかった様々なオイルも注目されるようになってきました。
しかし、私たち日本人の日常的な食卓では、その活躍の幅はまだまだ狭く、真新しいノートのように真っ白な状態ではないでしょうか。 Olivenoteでは、読者の皆様の意見やオリーブノートアンバサダーへの参加を募りながら、カラダに美味しいオイルを中心に、楽しく健康的な食卓を築いて行ける情報を綴ってゆきます。